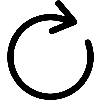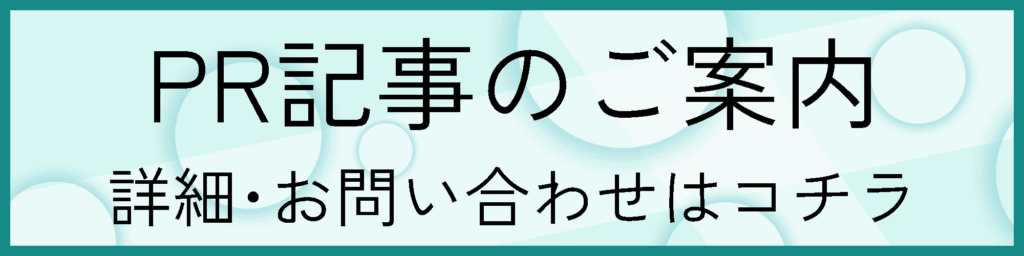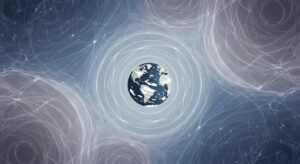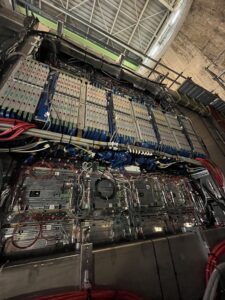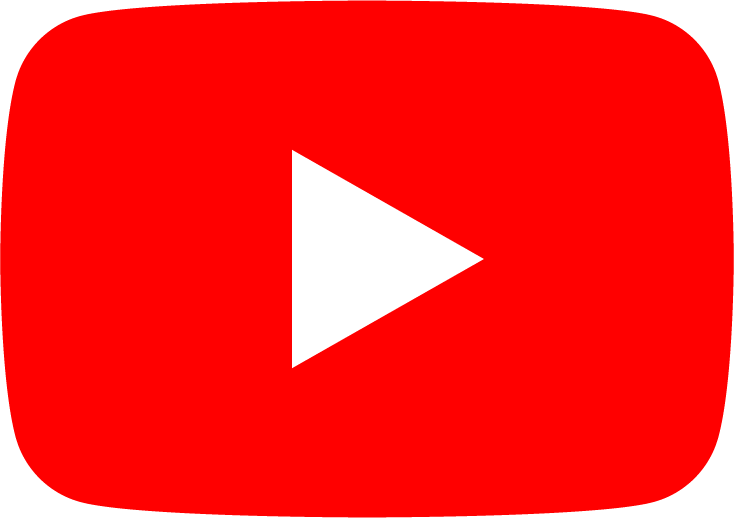1930年2月18日、ある”退屈な作業”が宇宙観を変えた
1930年2月18日、アリゾナ州フラッグスタッフ。薄暗い天文台の一室で、24歳の青年が顕微鏡を覗き込んでいた。彼の目の前には、同じ星空を撮影した2枚の写真乾板。点滅比較器と呼ばれる装置が、1秒に3回画像を切り替える。「パチッ、パチッ、パチッ」──単調なリズムの中で、青年は何千もの星の中から、ただひとつ「動くもの」を探していた。
青年の名はクライド・トンボー。高校卒業後、自作の望遠鏡で描いた火星スケッチをローウェル天文台に送り、助手として雇われたアマチュア天文家だった。天文台が探していたのは「海王星の外側にある未知の惑星(Planet X)」。その探索は、膨大な写真乾板を1枚ずつ比較する、気が遠くなるような単純作業だった。
そして、この日。1月に撮影された写真乾板を点滅させた瞬間、トンボーはわずか数ミリだけ動く光点を捉えた。これが、後に太陽系第9惑星(現在は準惑星)となる冥王星だった。
だが、この発見の本質は”何が見つかったか”ではない。”どう見つけたか”にある。トンボーは後年、ローウェル天文台での在籍期間(約14年)のうち、点滅比較器の覗き口に向かっていた時間を「約7,000時間」と本人が推計している。この”退屈な繰り返し”は、AIが27,500個の小惑星を発見する2026年に、何を語りかけるのか?
点滅比較器 ─ “人間版アルゴリズム”の解剖学
トンボーの「ワークフロー」を分解する
クライド・トンボーによる冥王星の発見は、単なる偶然や天才のひらめきによるものではありませんでした。それは極めて体系的な「データ処理プロセス」の結果だったのです。
ステップ1:データ取得
ローウェル天文台の13インチ望遠鏡を使用し、同じ星域を数日間隔で2回撮影します。1枚の写真乾板には、数万から数十万個もの星が写し出されます。
ステップ2:前処理
2枚の乾板を「点滅比較器(Zeiss Blink Comparator)」にセットします。顕微鏡で拡大しながら、星域を区画ごとに細かく精査していきます。
ステップ3:パターン認識
装置が1秒に3回画像を切り替えます。背景の星は静止して見えますが、太陽系内の天体だけが「ジャンプ」したように動いて見えます。このわずかな動きを目視で検出するのです。
ステップ4:検証
候補となる天体を発見した後は、軌道計算と追跡観測によって「小惑星か、あるいは惑星か」を判定します。写真乾板の傷、ゴースト、流星といった「偽陽性」を排除する作業です。
トンボーがこのプロセスに費やした時間は膨大でした。発見までの約1年間で調査した乾板は数百組にのぼり、14年間のキャリア全体では、点滅比較器の前で合計7,000時間を過ごしたと推定されています。
これは「手動CNN」でした
現代の視点で見れば、トンボーの作業は機械学習の「畳み込みニューラルネットワーク(CNN)」を人力で行っていたと言えます。
- 点滅比較器: 差分検出アルゴリズム(画像A – 画像B ≠ 0 を目視判定)
- トンボーの脳: パターン認識ニューラルネット(背景ノイズ vs 移動天体の分類)
- 軌道計算: 予測モデルによる検証フェーズ
しかし、1930年の人間には、2026年のAIにはない強みがありました。 写真乾板には、星以外のノイズが無数に写り込みます。ガラス面の傷、現像ムラ、光学系のゴースト、たまたま通過した流星などです。トンボーはこれらの「偽陽性」を直感的に除外しました。「なんとなくおかしい」という感覚、つまり文脈理解と経験則による瞬時の判断こそが、彼の武器だったのです。
そして何より、7,000時間もの単調な作業に耐え抜く意志力。これこそが、冥王星発見を可能にした真の「アルゴリズム」だったのかもしれません。
2024年、AIは数週間のクラウド計算で27,500個の小惑星を発見
THOR:トンボーの”デジタル後継者”
それから94年後、トンボーのワークフローは完全に自動化されました。 2021年、天文学者たちはTHOR(Tracklet-less Heliocentric Orbit Recovery)と呼ばれるアルゴリズムを発表しました。従来の小惑星発見手法は、同一天体の連続観測データである「トラックレット」を必要としていましたが、観測条件が悪ければ天体を見逃してしまう欠点がありました。
THORは逆転の発想を採用しています。まず理論上の軌道を数百万通り生成し、それを過去の観測データと照合するのです。「どの軌道であれば、この観測結果を説明できるか?」と逆算することで、バラバラの観測データから同一天体を特定します。
2024年、THORはGoogle Cloudの計算リソースを活用してアーカイブ画像を解析しました。その結果、27,500個の新小惑星を発見したのです(うち100個は地球近傍天体NEA)。旧世代のアルゴリズムと比較して検出効率は格段に向上し、トンボーが14年かけた作業を、わずか数週間で実行してしまいました。
Vera C. Rubin Observatory:「データ洪水」の到来
さらに圧倒的な変化が、今まさに始まろうとしています。 2025年、チリのVera C. Rubin Observatory(ベラ・ルビン天文台)が稼働を開始しました。この天文台のLSSTカメラは3,200メガピクセルを誇り、スマートフォン260台分のセンサーを持つ史上最大のデジタルカメラです。
10年間の観測プロジェクト「Legacy Survey of Space and Time(LSST)」では、南天全域を反復観測し、毎晩20テラバイトもの画像データを生成します。総データ量は、生データだけで60ペタバイトに達します。 この膨大なデータから、毎晩数百万もの変動天体(超新星、小惑星、変光星、重力レンズ現象など)が自動検出される見込みです。
1930年、トンボーは1枚の乾板を分析するのに数時間を要しました。しかし2026年現在、ルビン天文台は一晩で膨大な数の画像を生成し続けています。もはや、人間が生涯をかけても処理不可能な規模に達しているのです。
では、果たして人間は不要になったのでしょうか?
なぜ「退屈な繰り返し」が革新を生むのか?
歴史が証明する”地道な作業”の価値
科学史を振り返れば、偉大な発見の多くは「退屈な繰り返し」の先にありました。
ロザリンド・フランクリンの「Photo 51」
1952年、DNA二重らせん構造を示すX線回折写真「Photo 51」は、62時間のX線照射を要する精密作業の結晶でした。このデータがワトソンとクリックのノーベル賞受賞につながりましたが、フランクリン自身は生前に正当な評価を受けることはありませんでした。
キャサリン・ジョンソンの手計算
マーキュリー計画では、宇宙飛行士の軌道計算を「人間コンピュータ」が手作業で実行していました。数学者キャサリン・ジョンソンの計算は極めて正確で、宇宙飛行士ジョン・グレンは「コンピュータの結果を彼女にチェックしてもらえ。彼女が良いと言うなら飛ぶ」とまで言ったと伝えられています。
共通点は明確です。“退屈な繰り返し”の先に、誰も見たことのない景色があるのです。
AI時代における”7,000時間”の再定義
では、自動化できる作業に人間が時間をかける意味は、もうないのでしょうか?
3つの視点から考えてみましょう。
1. 異常の直感
トンボーは「なんとなくおかしい」星の並びを検出しました。AIは統計的外れ値を見つけることはできますが、「おかしさの質」を判断することは苦手です。写真乾板の傷なのか、本物の天体なのか。その文脈理解は、経験を積んだ人間の直感に依存します。
2. 問いの設定
トンボーは「どこを探すべきか」を判断しました。AIは”探索範囲”を人間に指定してもらう必要があります。つまり、AIは”答え”を高速化するが、”問い”を立てるのは人間なのです。
3. セレンディピティ
単調作業の中で、予期しない発見が生まれることがあります。トンボーも冥王星以外に多数の小惑星や変光星を発見しました。AIは「探すべきもの」しか探せませんが、人間は「探していなかったもの」に気づくことができます。
未来の天文学者は、何に7,000時間を使うべきか?
ハイブリッドモデルの台頭
すでに、人間とAIの協働モデルが成果を上げています。
NASA資金提供のプロジェクト「Backyard Worlds: Planet 9」では、世界中の市民科学者が「9番目の惑星(未発見の太陽系第9惑星)」を探索しています。AIが事前スクリーニングを行い、人間が最終判定を下すこのハイブリッドモデルでは、発見精度が更に向上しました。
2017年には、市民科学者が「9番目の惑星候補」を発見しています。これらは、AIだけでは”ノイズ”と判定されていた天体でした。人間の直感が、見逃されかけた発見を救出したのです。
2030年代の天文学者の仕事
では、Rubin Observatory時代の天文学者は何をするのでしょうか?
役割は明確に変化します。
- データ収集: AI/ロボット天文台が自動化
- 異常検出: THOR等のアルゴリズムが一次スクリーニング
- 人間の役割:
- 科学的仮説の立案(「なぜこの天体は奇妙なのか?」)
- 観測戦略の設計(「どこを、どう観測すべきか?」)
- セレンディピティの発見(AIが”ノイズ”と判定したものの再評価)
Rubin Observatoryが「毎晩数百万の変動天体」を検出する時代。人間は“100万個に1つの異常”を見極める役割へとシフトします。
そう考えると、トンボーの7,000時間は、単なる労働時間ではありません。それは”異常を見抜く直感”を養うトレーニング期間だったのです。
イノベーションは”退屈さ”の向こう側にある
1930年、クライド・トンボーは7,000時間の”退屈な繰り返し”で冥王星を見つけました。2026年、AIは27,500個の小惑星を瞬時に発見します。
だが、次の”冥王星”─つまり、私たちの宇宙観を根底から変える発見─を見つけるのは、依然として”退屈さに耐える力”を持った人間かもしれません。
スタートアップの世界も同じです。初期の”泥臭いユーザーヒアリング”、”手動オペレーション”、”A/Bテストの繰り返し”。そうした地道な作業が、後のプロダクト・マーケット・フィット(PMF)を生み出します。
2030年代、THORの次世代版は「AIが見つけた異常をAIが検証する」自律システムへと進化するでしょう。けれども最後に「これは本当に重要か?」を判断するのは、”退屈な繰り返し”を経験した人間の直感です。
あなたは、自分の7,000時間を何に使いますか?
【用語解説】
点滅比較器(Blink Comparator)
天文観測用の光学装置。同じ星域を異なる時刻に撮影した2枚の写真乾板を、1秒に3回のペースで交互に表示することで、移動する天体(惑星、小惑星、彗星)や変光星を目視で検出。1900年代初頭にドイツのZeiss社が開発し、冥王星発見後も小惑星探索に広く使用された。
THOR(Tracklet-less Heliocentric Orbit Recovery)
2021年発表の小惑星発見アルゴリズム。従来手法と異なり、「同一天体の連続観測データ(トラックレット)」を必要とせず、理論軌道を数百万通り生成して観測データと照合する逆算アプローチを採用。Google Cloud上で稼働し、2024年に27,500個の新小惑星を発見。Vera Rubin Observatory時代の”データ洪水”に対応する次世代技術として期待される。
Vera C. Rubin Observatory ── “史上最大の時間軸カメラ”
チリに建設された次世代天文台。2025年から本格稼働。3,200メガピクセルのLSST Camera(史上最大)を搭載し、10年間で南天全域を反復観測する「Legacy Survey of Space and Time(LSST)」を実施。毎晩20テラバイトの画像データを生成し、数百万の変動天体(超新星、小惑星、重力レンズ現象など)を自動検出。総データ量は生データで60ペタバイトに達する見込み。
📊 データ比較:1930年 vs 2026年
| 項目 | 1930年(トンボー) | 2024年(THOR) | 2026年〜(Rubin) |
|---|---|---|---|
| 発見数 | 1個(冥王星) | 27,500個(小惑星) | 年間数百万天体予測 |
| 処理時間 | 7,000時間(14年) | 数週間 | リアルタイム |
| データ量 | 数百枚の乾板 | アーカイブ数TB | 毎晩20TB |
| 検出方法 | 目視による差分検出 | 軌道逆算アルゴリズム | AI+自動パイプライン |
| 人間の役割 | 全工程を手動実行 | アルゴリズム設計・検証 | 仮説立案・異常評価 |
【参考リンク】
Lowell Observatory「History of Pluto」(外部)
Vera C. Rubin Observatory公式サイト(外部)
【編集部後記】
この記事を執筆するにあたり、私自身が「7,000時間」という数字に圧倒されました。1日8時間働いたとして、約2年半。トンボーはそれを14年間、断続的に続けたのです。
AIが秒速で答えを出す時代だからこそ、「なぜその問いを立てるのか?」「なぜその異常に気づくのか?」という人間の直感が、ますます価値を持つのではないでしょうか。