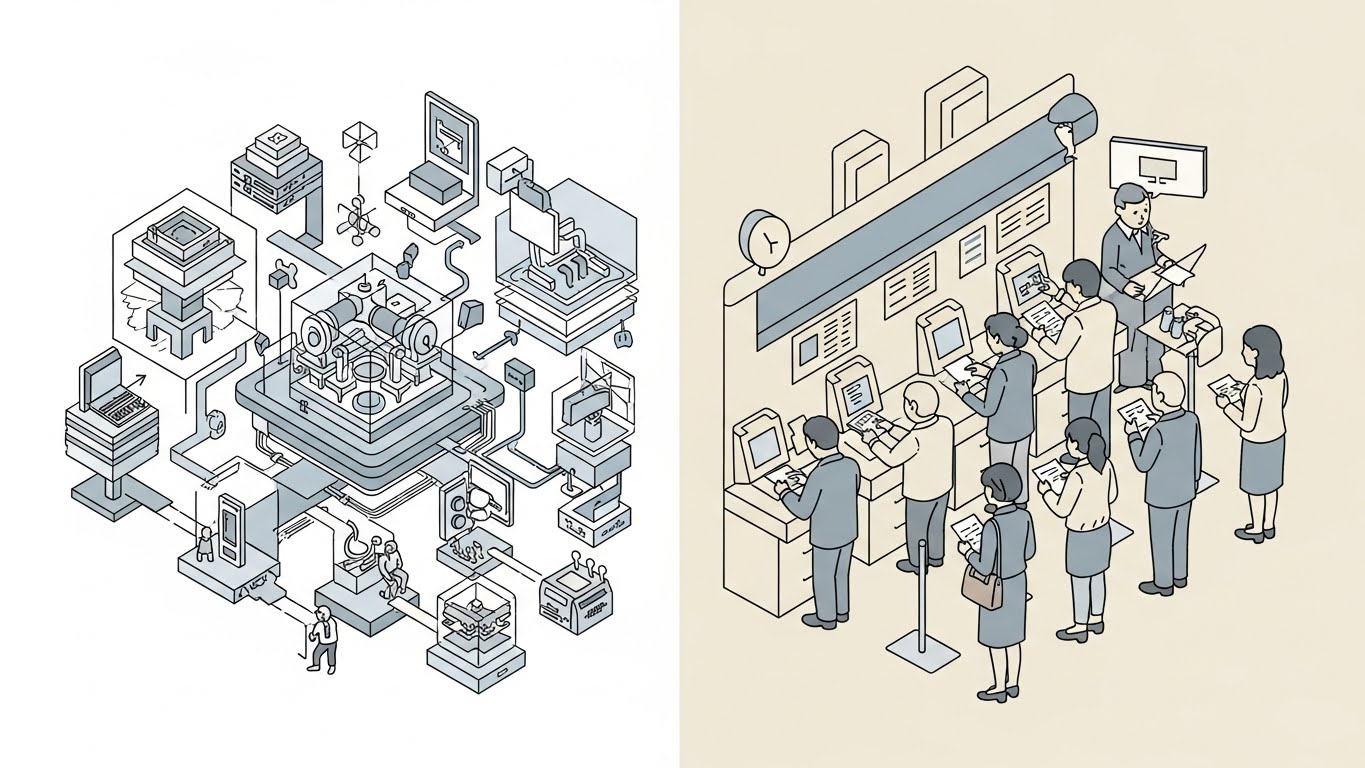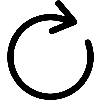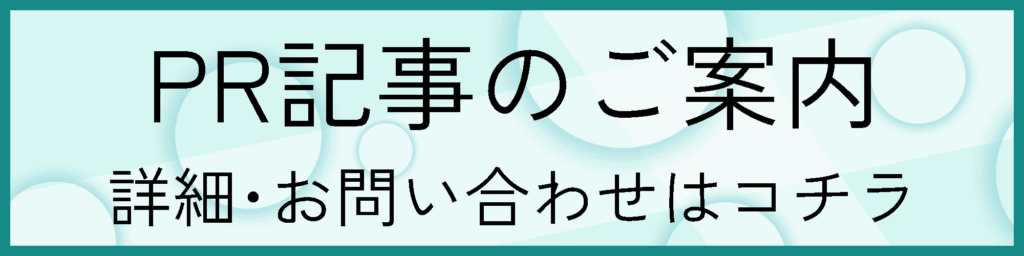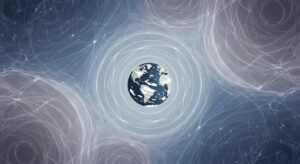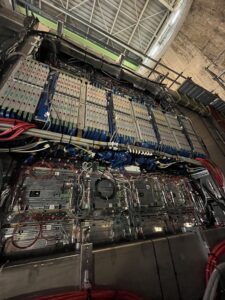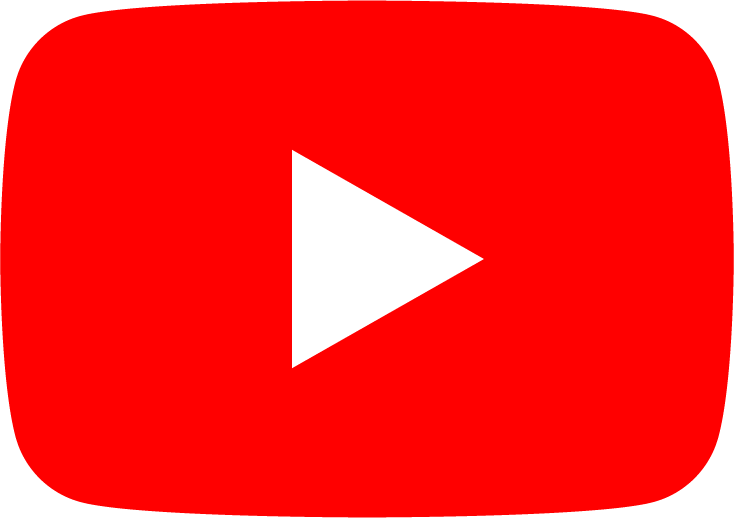営業活動は、これまで「成果の要因が言語化・共有されにくい仕事」のひとつだった。
誰が、どんな意図で、何を伝え、相手がどう反応したのか。その多くは商談の場に散逸し、記録が残っても個人の解釈に留まりやすい。DXが叫ばれる中でも、営業は依然として属人性の高い領域として扱われてきた。
その背景には、SFAを導入してもなお解決しない課題が残り続けていることがある。入力が形骸化すれば、情報は個人の解釈にとどまる。結果として、組織としての学習や再現性の構築が進まないケースも少なくない。
加えて、AIの進化とともに「AI時代に営業の仕事は奪われるのか」「人は何を担う仕事として残るのか」といった問いが、現場レベルでも現実味を帯び始めている。
では、営業のプロセスそのものがデジタル化され、提案内容や顧客の反応がデータとして蓄積されるようになったとき、AIは営業という仕事をどこまで理解し、支援できるようになるのだろうか。そしてその先で、人間にしか果たせない役割はどこに残るのか。
本稿では、デジタルセールスルーム「openpage」を展開する株式会社openpage 代表取締役の藤島誓也氏に、営業DXの現在地と、営業活動が「AI処理可能なデータ」になりつつある時代の構造について寄稿いただいた。
AI時代の営業はどのように変わり、仕事の本質はどう再定義されていくのか。そのヒントを、現場と思想の両面から読み解いていく。

藤島誓也
株式会社openpage代表取締役。キヤノンマーケティングジャパン、伊藤忠テクノロジーベンチャーズと資本提携。デジタルセールスルーム(DSR)による”眼前可視化営業”で日本企業の営業変革を推進。 2018年創業以来、前年比837%成長を実現。ビックカメラをはじめとする大手企業への導入実績を持ち、商談化率平均2.5倍、営業データ量10倍増加の成果を創出。国内DSRカテゴリーでトップシェアを確立している。 エンジニア、デジタルマーケティング、メディアビジネス、営業企画と10数年の横断的キャリアを構築。この多様な経験を活かし、データとデジタルを起点とした営業変革に取り組む。著書「実践カスタマーサクセス」(日経BP)、NHK Eテレ出演など情報発信も積極的に行っている。
株式会社openpage公式サイト:https://www.openpage.jp/
ある製造業の営業部長から相談を受けた。「若手がデジタルツールばかり使いたがって、顧客と会おうとしない。これで本当に売れるのか?」
私は答えた。「問題は、会う・会わないではありません。営業プロセスの中に、デジタルとアナログをどう織り交ぜるか、です」
この会話は、今起きている営業の構造転換を象徴している。私自身、デジタルセールスルーム「openpage」を開発・提供する経営者として、この逆説を日々目の当たりにしている。営業のデジタル化は単なる「ツールの導入」では終わらない。これは人間とAIの役割分担という、根本的な問いかけなのだ。
営業活動のデータ化が生む構造転換
まず押さえておくべき事実がある。営業活動のデジタル化は、もはや「やるかやらないか」の段階ではない。米国のテクノロジー企業では、デジタルセールスルームの活用は標準装備だ。Salesforceの2024年の調査によれば、B2B購買担当者の80%が「営業担当と会わずに購買判断を完結したい」と回答している。
この数字をどう捉えるべきだろうか。営業担当からすれば危機感かもしれないが、顧客から見れば極めて合理的な態度だ。必要な情報を自分で読んで判断したい。忙しいのは営業だけではない。
この変化の背景にあるのは、営業も顧客もミレニアル世代以降が中心になってきたという人口動態的な転換だ。彼らはSlackやNotionでのコラボレーションに慣れている。非同期コミュニケーションの方が効率的だと考えている。
興味深いのは、ここで構造的な転換が起きているという点だ。デジタルセールスルームを使うことで、営業提案そのものがデータになるのだ。
従来の営業では、提案資料をメールで送り、商談で口頭説明し、議事録を別途作成していた。これらは断片化され、記録も曖昧だった。しかしデジタルセールスルームでは、提案内容の共有、顧客の閲覧履歴、質問と回答のやり取り、商談の議事録が一つのプラットフォーム上に統合される。すべてがタイムスタンプ付きのログとして蓄積される。
つまり、営業提案をデジタル化することで、初めてAI処理が可能になる。紙の資料やバラバラのメールでは、AIは何も分析できない。すべてが一つのデジタル空間に集約されるからこそ、パターン認識が可能になる。
エンジニア時代の私は、この「データの統合と構造化」の重要性を痛感していた。散在するログファイルを一つのデータベースに集約し、クエリ可能な形式に整える。そうして初めて、分析や自動化が可能になる。営業の世界でも、まったく同じことが起きている。
AI時代だからこそ、対話が起点になる
openpageが「眼前可視化営業」と呼んでいるスタイルがある。顧客とのヒアリング内容を、デジタルセールスルーム上にリアルタイムで投影しながら、目の前でインタラクティブに記入していく手法だ。
一見、デジタル時代に逆行するアナログなやり方に見える。しかし、この問いかけ自体が本質を見誤っている。経営層は「効率化」を求め、現場は「顧客との関係性」を重視する。一見対立するように見えるが、実際には両立可能なのだ。
なぜなら、AI時代だからこそ、対話というアナログな行為が起点になるからだ。
顧客の本音は、用意された資料だけでは出てこない。「実は、導入を検討しているのは私だけで、上司は懐疑的なんです」「過去に似たツールを導入して失敗した経験があります」。こうした生々しい情報は、対話の中で、相手の表情や言葉の間から読み取る必要がある。
そして、その対話の内容を、その場でデジタルセールスルーム上に記録していく。顧客が見ている画面に、リアルタイムで議事録が形成されていく。「今日お話しした内容はこれで合っていますか?」と確認しながら。この行為自体は、AIには実行できない。人間の判断、共感、即興性が必要だからだ。
しかし、ひとたびデジタルセールスルームに格納されれば、そこから循環が始まる。
デジタル化されたヒアリング内容は、顧客が後から見返し、社内メンバーと共有し、追加の質問を投げかける。その反応をデータとして確認できる。「どのセクションを何度も読み返しているか」「どこで新しいメンバーが参加したか」。
蓄積されたデータをAIが処理する。「この顧客の懸念点は何か」「次にどの資料を共有すべきか」「類似案件での成功パターンは何か」。AIが過去のデータと照合し、提案を返してくれる。
ただし、AIの提案を鵜呑みにしてはいけない。営業担当が判断する。「この提案は、今回の顧客の文脈に合っているか」。人間が咀嚼し、修正し、最終的なアクションを決める。
そして、また対話に戻る。対話 → デジタル格納 → データ化 → 反応確認 → AI処理 → 人間の判断 → また対話。この循環が、営業プロセスそのものになる。
営業体験の凝縮が生む劇的な変化
この循環が生み出すインパクトは大きい。デジタルセールスルームを活用することで、商談のリードタイムは30%近くまで削減でき、受注率も10〜20%の改善余地がある。
なぜこれほどの改善が可能なのか。
従来であれば、対話の中身を振り返るには次回の商談を待つ必要があった。次回までの設定期間は平均2週間。その間、顧客は待つしかない。しかし、デジタルセールスルームがあれば、顧客は自律的に情報収集できる。疑問が浮かんだらその場で資料を確認し、追加質問を投げかける。
物理的な商談は2週間後でも、デジタル上では毎日「対話」が続いている。このマイクロな対話の積み重ねが、意思決定を加速させる。
ここで重要な視点がある。B2B購買サイクルの延長は、見方を変えれば、顧客が新しい取り組みを社内企画して承認されるまでのスピードでもある。
顧客自身も、企画の長期化は望ましい姿ではない。社内の関係者を巻き込み、合理的な意思決定を紡ぐプロセスは、従来6〜12ヶ月かかっていた。企画の整理、データの収集、各部門との調整、上層部への説得。これらがすべてアナログだったからだ。
しかし、デジタルとAIで凝縮された営業体験を提供することで、このプロセスを短縮する余地は大いにある。
例えば、CFO向けのROI計算シート、現場責任者向けの導入スケジュール、IT部門向けのセキュリティ資料、経営層向けのエグゼクティブサマリー。これらを、デジタルセールスルーム上に整理して提供すれば、顧客は各部門と並行して調整を進められる。
さらに、AIが論理性を提供する。「この投資判断を正当化するには、どの数値を示すべきか」「過去の類似案件では、どのポイントが承認の決め手になったか」。AIの分析が、顧客の社内説得を助ける。
これがバイヤーイネーブルメントだ。顧客を「購買担当者」ではなく、「社内の変革推進者」として支援する。バイヤーイネーブルメントによって、成約までの期間が短縮される。
新世代のトップ営業:パーソナライズされた営業体験
この構造変化は、トップ営業の定義をも変えつつある。
ベテラン営業は「足で稼ぐ」ことを美徳とし、若手営業は「データで判断」することを重視する。一見対立しているが、実はどちらも正しい。重要なのは、足で稼いだ情報をデータ化し、データから得た洞察を足で確認する、という循環を回すことだ。
そして、その循環の中で、まったく新しいタイプのトップ営業が生まれつつある。パーソナライズされた営業体験を創造できる営業だ。これは、従来のベテラン営業とはまったく性質の異なるスキルセットだ。
openpageでは、顧客の行動データを可視化し、営業担当が「いつ、誰に、何を」フォローすべきかを判断できる仕組みを提供している。「価格ページを3回以上閲覧しているが、導入事例は見ていない」という顧客には、ROIを示す資料ではなく、同業他社の成功事例を送る。
これがパーソナライズの基盤だ。一人ひとりの関心と状況に合わせて、提案をカスタマイズする。従来のベテラン営業も「顧客に合わせる」ことはしていた。しかし、それは経験と勘に頼っていた。今は、データがそれを裏付け、再現可能にする。
AIとのコラボレーションも重要だ。「この提案のどこを改善すべきか」をLLMに問いかけ、その出力を咀嚼しながら、自分なりの提案ストーリーを組み立てる。上司との1on1は週1回が限界だが、AIとなら1日に10回、20回とイテレーションを回せる。この高速イテレーションが、パーソナライズを可能にする。
顧客Aの組織は稟議プロセスが厳格だから、より詳細な資料が必要。顧客Bの組織はトップダウンで意思決定が速いから、経営層向けの1枚資料が有効。一人ひとりの顧客の組織構造と意思決定プロセスに合わせて、提供する情報をカスタマイズする。
従来のベテラン営業とはまったく性質の異なるトップ営業を、今後の営業の世代は作ることができる。それは、デジタルとAIを駆使しながら、一人ひとりの顧客にパーソナライズされた営業体験を提供できる営業だ。
営業組織に必要な3つの要素
個人の努力だけでは限界がある。営業組織全体として、AI時代に適応するためには、3つの要素が必要だ。
1. 営業プロセスの中にデジタルを自然に織り込む
従来のSFA(営業支援システム)の問題は、営業活動の「後」に、事務作業としてデータ入力を求める点にあった。これは面倒だ。だから、入力されない。
発想を転換すべきだ。営業プロセスそのものをデジタル空間で行えば、データ入力は不要になる。デジタルセールスルームのopenpageを使えば、対話の内容をその場でデジタル上に記録する。提案を共有すれば、自動的に顧客の閲覧履歴が記録される。営業プロセスの中に、デジタル、データ、AIが自然に織り交ぜられる。
2. AIが分析し、人間が判断する循環を回す
蓄積されたデータをAIが分析し、営業担当にフィードバックする。「あなたの提案は、初回商談の段階から離脱率が高い」「この顧客には、この導入事例を見せた方が効果的」。
重要なのは、フィードバックが具体的で、実行可能であることだ。そして、AIの提案を、具体的な営業改善につなげるまで、人間がちゃんと判断し、実行し、検証する。このサイクルを繰り返す。検証結果が、また新しいデータとしてAIに返される。循環が回る。
3. 人間が対話に集中できる環境
営業担当の時間の多くは、資料作成、データ入力、社内調整といった非本質的な業務に費やされている。openpageでは、テンプレート機能やAI補助機能を活用することで、提案資料の作成時間を大幅に削減できる。ある導入企業では、営業担当の資料作成時間が平均40%削減されたというデータがある。その時間が、顧客との対話に振り向けられる。循環の起点である「対話」に、より多くの時間を使えるようになる。
あなたの営業組織は、どう変わるか
ここまで書いてきた内容は、単なる未来予測ではない。Gartnerのレポートによれば、2024年時点でFortune 500企業の65%が、何らかの形でデジタルセールスルームを導入している。日本でも、ミレニアル世代以降が営業の中心になるにつれ、この流れは加速している。
重要なのは、対話 → デジタル格納 → データ化 → 反応確認 → AI処理 → 人間の判断 → また対話。この循環を、あなたの組織に最適な形で回すことだ。
業界によって、企業文化によって、顧客層によって、循環の速度や重点の置き方は異なるだろう。製造業の設備投資型営業と、SaaSのサブスクリプション型営業では、デジタル化の進め方も変わる。
しかし、どの業界であれ、営業プロセスの中にデジタル、データ、AIを自然に織り交ぜることは可能だ。そして、それによって営業担当は「対話」に集中できるようになる。パーソナライズされた営業体験を提供できるようになる。
あなたの営業組織では、デジタルと人間の分業体制はどのような形になるだろうか。営業担当が本当に価値を生む「対話」に集中するために、何から始めるべきだろうか。
答えは一つではない。大切なのは、この循環を自分たちの組織に合わせて設計し、回し始めることだ。そのプロセスの中で、あなたの組織独自の最適解が見えてくるはずだ。
【用語解説】
デジタルセールスルーム(Digital Sales Room)
営業担当と顧客が提案資料、製品情報、質疑応答などを一元管理できるオンライン上の共有スペース。従来のメールや会議資料の散在を解消し、営業プロセス全体を可視化・効率化する。顧客側も社内メンバーと情報を共有しやすくなり、購買プロセスが加速する。米国では「Digital Deal Room」とも呼ばれる。代表的なツールとして、Seismic、Highspot、Docsend、そして日本発のopenpageなどがある。
バイヤーイネーブルメント(Buyer Enablement)
顧客が購買意思決定をスムーズに進められるよう支援する営業手法。具体的には、社内稟議用の資料、ROI計算ツール、導入事例、FAQ集などを提供し、顧客が社内の意思決定者を説得できるよう支援する。従来の「営業が売る」から「顧客が買えるようにする」への転換を意味する。Gartnerの調査によれば、B2B購買の意思決定には平均6〜10人が関与しており、営業担当が全員と会話することは不可能に近い。だからこそ、顧客自身が社内で推進できるよう支援する必要がある。
非同期コミュニケーション(Asynchronous Communication)
リアルタイムでの応答を必要としないコミュニケーション手法。メール、チャットツール、共有ドキュメントなどを通じて、各自が都合の良いタイミングで情報を確認・返信する。対義語は「同期的コミュニケーション」で、電話や対面会議などのリアルタイムのやり取りを指す。リモートワークの普及により、非同期コミュニケーションの重要性が増している。
LLM(Large Language Model / 大規模言語モデル)
膨大なテキストデータで学習された大規模なAIモデル。ChatGPT、Claude、Geminiなどが代表例。自然言語での質問に対して、人間のような回答を生成できる。営業においては、提案書のドラフト作成、顧客からの質問への回答案作成、商談後の議事録作成などに活用される。ただし、生成された内容は必ず人間が確認・修正する必要がある。
【参考リンク】
営業DXとデジタルセールスルームに関する情報
- Gartner – Sales Technology(外部)
Gartnerによる営業テクノロジーの調査・分析 - Salesforce Research(外部)
Salesforceによる営業・マーケティングに関する調査レポート
AI技術と営業の融合
- McKinsey & Company – Sales & Marketing(外部)
AI活用を含む営業変革に関する考察 - Harvard Business Review – Sales(外部)
B2B営業の最新トレンドと研究
テクノロジートレンド全般
- Forrester Research – Sales Enablement(外部)
営業支援技術とバイヤーイネーブルメントに関する分析 - TechCrunch(外部)
セールステック領域の最新ニュース
デジタルセールスルーム関連
- Digital Sales Room Category – G2(外部)
デジタルセールスルーム製品の比較・レビュー
【関連書籍】
- 『実践カスタマーサクセス』藤島誓也著(日経BP)- 顧客との長期的な関係構築とデジタル活用について
https://bookplus.nikkei.com/atcl/catalog/22/12/06/00539/
【関連記事】